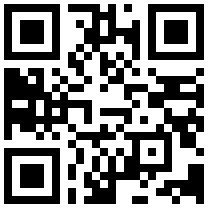業界の裏話をちょっとしたいと思います。
昨日ある方と展示場でお話をしていた時のこと。
『明工さんってかなり安いけれど、これ会社としてやっていけないくらいの利益削ってるでしょ?』
とそんな話になりました。
話をしていた方も、ある意味業界の方でしたので、何となく相場が分かるのから当社の価格が異常だと思ったのでしょう。
そして、その為には相当利益を削らないといけないと思い込まれたわけです。
実情は確かに高額な利益をもらってはいませんが、会社としては成り立つ利益はもらっています。
同業者だから、仕入れ値が分かるからとしての疑問だったのでしょうが、大きな隔たりがあるように感じました。
このように同業者なのに、話が食い違う理由があることを、本日は少しお話したいと思います。
一般人だと理解出来ない!?売り値は人によって変わるものです。
最初に答えを言ってしまうと、今回お話ししていた同業の方と、当社では大きく仕入れ値が違うのことが原因でした。
簡単に言うと、当社が部材を買っている値段が、普通よりも格段に安いってことでした。
一般的な買い物だとあまり理解出来ない人も多いみたいですが、実は売り値って人によって変わってくるものなのです。
それは、例えばコンビニに比べてドンキの方が安いとか言ったことではなく、同じドンキで買ったのに、当社と同業者さんで値段が違うってことが起きています。
これはあまり理解が出来ない人が多いかもしれませんし、関西の方だと意外に飲み込みやすいと言われています。
これは偏見もあるかもしれませんが、大阪とかだと買い物のときに『お兄さん、なんぼまけてくれるの?』みたいな会話が普通にあると言います。
ある意味これと同じです。
私達が一般的な業者さんよりも安く売ってもらっているので、こういったことが起きています。
誰でもが安くしてもらえるわけではない
だったらどの同業他社さんも安くしてもらえば問題は解決だね!
と言うことになりそうですが、話はそう簡単にはいきません。
多分ですが、今回話をした同業の方は、当社が提示されている仕入れ値で買うことは出来ません。
理由は簡単で、毎回そんなことをしていたら、売る側が儲けが無くなってしまい商売あがったりになってしまうからです。
じゃー明工だけなんでそんなにひいきされてるの?って話になりますが、そこは企業努力と言うしかありません。
その理由としてあげられる簡単な答えとして言えるのが、私達は安く売ってもらっているかもしれませんが、それ以上の価値やお金をその業者さんに与えているということです。
いわば『WIN-WIN』の関係、さらにそうして出来た安価で性能の良い家を買えるお客さんも『WIN』なので、『WIN-WIN-WIN』の関係だと言えます。
この状態を作るのに、当社は約55年の月日が掛かりました。
創業以来55年の信頼や、取引形態、さらには業者さんとの協力関係を最大限に利用し、今の仕入れ額を手に入れました。
また、取引業者さんに有利になるような条件も付け加えることで、今後も値引きを得られやすい環境を作るなどの努力をしています。
そういった努力をし続けられる会社であるから、55年間も皆さんのご愛顧を頂けたわけです。
じゃあどのくらい違ったのさ?
ここまで話されると、『じゃあ明工とその業者さんどのくらい違ったのさ』って聞きたくなりますよね。
当然企業秘密の部分ですので、正確な金額はお話しは出来ませんが、ある程度分かるニュアンスで今回はお話をしていこうと思います。
私とその業者さんとの会話ででた金額は、およそ10%程度開きがありました。
なので、この業者さんとの仕入れの差もだいたい10%前後位だと思います。
たった10%かー思ったより普通だな・・・
なんて思われた方!
確かに10%なので、数字としてはそんなに大きくはないでしょう。
でも住宅の価格って2000万~3000万円です。
たった10%が200万円、300万円と化けてくるのです。
家一軒の利益は大手メーカーで40%、中小工務店で20%程度と言われていますので、2000万円の場合の利益は大手で800万円程度、中小工務店で400万円程度です。
当然各社この数字はバラバラなので、一概には言えませんし、実際に当社はこの数字とは違う数字になっています。
ちなみにこの数字は調べたら簡単に出てくるので、興味がある方は調べてみるのも面白いと思います。
さて、この利益の額を考えれば、200万円、300万円も違えば大きな差になると言うことです^^
今回の金額の差はこの通りでは無かったのですが、同業さんは信じられないって顔をしてこの事を聞いていました。
価格は上がっても、価値は止まっている?
ちなみにこんな話を聞いたことがありますか?
住宅、車、時計、飲食店など、あらゆるモノの価格はそれこそピンからキリまで色々な価格があります。
同じ時計でも100円で買える物もあれば数千万円するものもあります。
ですが、それにともなって「中身の価値」まで上がっているかといえば、必ずしもそうとは限りません。
たとえば、家なら断熱性や耐震性、車なら燃費や安全性能、時計なら時を刻む精度など、モノとしての基本性能はある一定のレベルに達すると、そこから先の価格差での進化はゆるやかになります。
つまり、性能としての「価値」はあるところで頭打ちになるのです。
それでも価格が上がり続けているのはなぜでしょうか?
それは、そのモノに“付加価値”がどんどん上乗せされているからです。
上がっているのは「物そのもの」ではなく「意味や雰囲気」
ブランド、デザイン、限定モデル、有名人の使用、希少性、ストーリー性——こうした「モノの外側」にある要素に、私たちは価格の多くを支払っています。
いわば“空気代”のようなものです。
例えば高級腕時計。100円のものと100万円のものがあったとして、時間の正確さはどちらも大きくは変わらないでしょう。
100万円の価格差のほとんどは、ブランドの価値や所有欲、見た目の雰囲気によるものです。
このように、価格の高さが=性能の高さや価値の高さを意味しない時代になっています。
住宅も同じ、大手メーカーの高い家は、家としての価値よりも、それに付随するものへの金額がおおくなります。
にもかかわらず、「高いから良いもの」「高いから間違いない」と考えてしまうのは、まさに感覚の錯覚と言えるかもしれません。
価格と価値の違いを知っているかどうかが分かれ道
商売をしている人たちは、こうした仕組みをよく知っています。
「この価格は、どこまでが中身で、どこからが付加価値か」を自然と見極めているのです。
しかし、一般の消費者はそうした視点を持つ機会が少ないため、「なんでも高いものが安心」と思い込んでしまいがちです。
これからの時代、モノを買うときには「その価格に見合う価値が本当にあるか?」「自分が必要としている“中身”にお金を払っているか?」という視点を持つことがとても大切です。
値上がりが続く中で、冷静に“本質”を見抜く力。それが、賢い選択につながっていくのではないでしょうか。
今回は少し違った切り口で、お金の話をしてみました。
今まである程度信じられてきた、大手メーカーのブランドはこれからは重要なファクターとは言えなくなるかもしません。
これまでのブランドや目に見えない価値に縛られてきた人は、頭の切り替えが必要かもしれません。
そこを大事にしていきたいのなら、そのままでも良いかもしれませんが、物事の本質をとらえた生き方をしたいなら、どちらが有利かどうかは火を見るよりも明らかですね。
今回は、ここまで。
では、また!